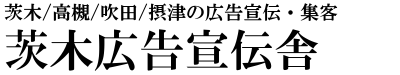JR西日本は24日に、近畿圏の終電時刻を繰り上げる検討を始めたことを発表しました。
終電から始発までの間の保線作業の時間を確保し、保線作業員の労働改善と人員確保をすることがひとつの理由ですが、他方で午後9時以降、とくに午前0時台の主要駅(大阪駅・京都駅・三ノ宮駅)の利用客数が減っていることがあるようです。
2013年度と2018年度を比較すると午後5~8時台の利用者数は3駅とも103~107%と増えているいっぽう、午後9~11時台は92~96%、午前0時台は81~88%と減っているようです。
JR西日本のプレスリリースがそうなのか、それともマスメディアのみなさんの解釈なのか知りませんが、この傾向を働き方改革の結果、残業が減ったととらえているようです。
しかしそれは一面的な見方だと思います。もっと大きな原因は単純に少子高齢化による生産年齢人口の減少だと思います。
総務省統計局の「人口推計(2018年(平成30年)10月1日現在)‐全国:年齢(各歳),男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級),男女別人口‐」を見てみましょう。
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2018np/index.html
その中でも下記の表を見てみます。
第1表 年齢(各歳),男女別人口及び人口性比―総人口,日本人人口(平成30年10月1日現在)(エクセル:45KB)
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2018np/zuhyou/05k30-1.xls
そこでこの5年間に退職した年齢(61~65歳※ここでは一律60歳定年と仮定します)と、この5年に就職した学卒者(23~27歳※浪人等は考慮しません)の人口を比較してみます。
前者は7758千人、後者は6242千人です。単純に計算すると6242÷7758=80.46%で、約20%減っている計算です。働き方改革のいっぽうでサービス業比率が高まっていることを考えると、主要駅の利用者が単純に働き手の減り方と同様に2割減らなくてもそれは自然といえるかもしれません。
また比較的早い時間帯はむしろ増えているのは、一億総活躍社会で女性の働き手が増えていることや、たとえば嘱託などで時間外勤務を課せられず働く高齢者が増えていることにあるでしょう。
少し話が本来書こうとしていたことから逸れました。
JR西日本が仮に0時台の終電を繰り上げたとしたら、大阪発のJR京都線は0:00新快速野洲行き、0:05普通高槻行、0:15普通京都行、0:25新快速京都行、0:31普通高槻行がなくなる可能性があります。
ちなみにその後には0:34寝台特急(サンライズ瀬戸・サンライズ出雲)東京行がありますが間違っても乗ってはいけません。次の停車駅は静岡です。
私鉄の動向も見ながらということですから、阪急京都線の0時台の梅田発が0:00準急桂行、0:10高槻市行、0:25正雀行であることを考えても、JR京都線も0:15以降がなくなっても不思議ではありません。
たった15分ほどの繰り上げでも、心理的な影響は少なくないでしょう。仮に30分繰り上げるとさらに影響はおおきくなります。
おそらく遅い時間の「チョイ飲み」がなくなります。かつて会社勤めしていたころは、10時すぎまで残業しても「1杯だけ飲んでいこう」「1時間勝負で」と飲みに行きました。
これが11時半ごろには電車を気にするようになると、「もう寄り道せずに帰ろうか」ということになります。そうすると中には最寄り駅の飲食店を利用する人が増えるはずです。
たとえば、JR茨木駅に近い茨木広告宣伝舎のオフィスの近所にある「ゆうらい」というラーメン屋さんは、0時すぎになるとサラリーマンぽいお客さんがかなり入っています。
またラーメン屋さんで恐縮ですが、阪急茨木市駅に近い「福ちゃんラーメン」も終電くらいの時間に入るとほぼ満席です。
これらの人の多くは、おそらく仕事のあとにそのまま茨木まで帰ってきて、家に帰るまでにビール一杯、ラーメン一杯を食べようというのでしょう。これからはそうした人が増えると思います。
そしてそれは当然茨木だけではなく、吹田・岸辺・千里丘・JR総持寺・摂津富田・高槻の各駅商圏でも同じことが期待できます。ラーメン屋以外にも、居酒屋とか定食屋にも同様の効果はありえます。
もちろん、終電が早まることで早く帰るお客さんも増えるでしょう。JR茨木駅周辺の飲食店であれば、北おおさか信用金庫、西日本高速道路関連、JAF、公務員(大阪府・茨木市)などの従業員がお客さんだったりします。
しかし、大阪駅から流入する新規顧客と、地元駅から流出する既存顧客では、圧倒的に新規顧客のほうが多いのです。
このビッグウェーブに乗るために、深夜営業を検討していただき、ぜひウェブサイト(ホームページ)も開設して、深夜営業をアピールすべきでしょう。